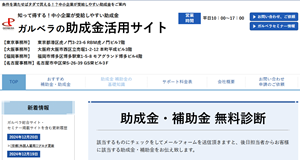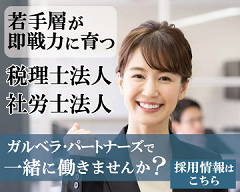IPO準備支援、M&Aの労務デューデリジェンスはお任せください

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ
労務監査.com
【東京事務所】東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
【大阪事務所】大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
【福岡事務所】福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
【名古屋事務所】名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
IPO・M&Aの労務監査
お気軽にお問合せください!
労務トラブルの発生パターン(臨検・労使紛争・訴訟)
未払残業やコンプライアンス違反による労務トラブルは、様々な形態があります。
大きく分けて「労働基準監督署により臨検」と「従業員からの請求」の2パターンがありこれまで潜在的リスクに過ぎなかった問題が、一挙に労務トラブルとして顕在化します。
IPOやM&Aにおいては、成長段階にある企業が多くなるのですが、これまで幸運にも労務トラブルが顕在化していなかった企業では、こうしたリスクに無防備になっていることが多くなっております。重要なタイミングでこうした労務トラブルが発生してしましますと上場申請の延期、またはM&Aのブレイクとなる場合もあり、案件の成否への影響はたいへん大きなものなります。
労働基準監督署の臨検

労働基準監督官は、労働基準法に基づいて事前予告なしに企業に対して立ち入り調査(臨検監督)を行うことができ、さらに刑事訴訟法に基づき事情聴取や証拠物品押収などの犯罪捜査や逮捕をする特別司法警察職員の権限も備えています。
①定期監督
その年の「地方労働行政運営方針」に従い、対象企業に対して実施されます。
<対象になりやすい企業>
「就業規則、36協定の未提出企業」「サービス残業が多そうな業種」
「労働災害が多い業種」「臨検で違反事項が多い企業」
②申告監督
従業員や元従業員による申告に基づいて労働基準監督署が臨検を行うこともあります。一般的には、申告があった場合、迅速に調査が行われ、立ち入り検査になる場合もあります。内容としては、賃金の不払い、解雇、パワハラなどのトラブルが多くなっています。
③災害時監督
一定規模以上の労働災害が発生した場合には、労働基準監督官が事故現場に赴き、臨検監督が行われて再発防止措置がとられます。
④再監督
定期監督、申告監督、災害時監督などを実施し、臨検監督を行った結果、法令違反があった場合、「是正勧告書」が交付されます。この法令違反が是正されているかどうかを確認するために臨検監督が行われることがあります。
従業員からの請求(あっせん、労働審判、訴訟、証拠保全手続、外部労組)

労働者からの請求もきっかけとなります。労働者が相談する外部機関は「労働基準監督署」「弁護士」「外部ユニオン」などがあり、それぞれパターンが異なります。
労働基準監督署へ相談がなされた場合は、違法性が疑われるケースでは上記②申告監督となります。こうした行政的なプレッシャーと合わせて、労働局のあっせんや訴訟などで民事的(未払賃金、慰謝料)な請求も行われるケースが多くなります。係争によるレピュテーション・リスク(風評リスク)のみならず、外部機関の介入による社内の動揺もありますので、IPOやM&Aへの悪影響は避けられません。
労務監査においては、このようなトラブルが起こりえないように、また起こったとしても会社の言い分を正しく主張できるように、リスク分析と対策提案を実施します。
①労働基準監督署の活用
未払賃金などの民事的な請求と前後して、労働基準監督署が活用されるケースがあります。従業員側の主張を認めさせるための材料として、プレッシャー効果も期待しての狙いになります。
都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など全国400カ所程度に総合労働相談コーナーを設置されており、専門の相談員(行政担当者や委託社労士など)があらゆる労働問題の相談にワンストップで対応しております。労働法令違反が疑われる案件については、会社に問い合わせや出頭の要求など、申告監督が行われるきっかけにもなります。
②労働局長の助言・指導
民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度です。事業主が労働局に呼び出しをされる場合もあります。
③あっせん
紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。訴訟とは異なり、両者の妥協点を探り、和解できるように促すような内容になります。
パートタイム労働者、入社歴の浅い社員、契約社員など、スピーディで簡潔な金銭解決を求めている場合は選択されやすいようです。
④労働審判
労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を裁判所において、原則として3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。
労働審判手続では、裁判官である労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が審理し、適宜調停を試み,調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)をします。労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。
短期での解決を望む場合 ある程度和解や譲歩の余地がある場合に選択されるようですが、訴訟類似の制度であり、弁護士への依頼が必要であることから、中小企業にとっては、訴訟類似の負担となります。
⑤民事訴訟
残業時間の立証に自信がある場合、和解の余地がない場合、付加金の支払いも視野に入っている場合は上記の手続を飛ばして従業員側代理人(弁護士)から訴状が届くケースもあります。
先方に代理人(弁護士)がついている場合は先だって証拠保全手続などが行われる場合があり(裁判官、弁護士、カメラマンなどが会社に突然やってきます)社内の動揺が懸念されます。
⑥外部ユニオンへの加入
労働者が外部の労働組合(ユニオン)に相談することにより、会社 対 ユニオンという交渉に拡大します。会社は交渉を拒否できないため、対応に膨大な労力を要します。
労働者が外部ユニオンに駆け込んだ場合は、紛争が拡大しやすく、他の従業員への波及の可能性もあります。街宣などが行われる場合もあり、社内の動揺が懸念されます。
未払残業代請求に関する法律上の問題点

◆賃金債権の消滅時効
労働基準法第115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
一般によく知られているように、賃金の消滅時効は2年です。IPOを目指す場合には少なくとも上場申請の2年前までには未払残業対策をしなければなりません。すなわち直前前期に突入する前には対策を完了して上場申請時にはクリアランスが確保されていなければなりません。
対策が遅れた場合は、全ての未払債務を精算するか、退職者も含めた対象社員の個別同意を取り付けることになりますので、膨大な手間になります。
IPOをご検討の会社にとっては、未払残業は最優先で対策すべき経営課題となり、対策が遅れた場合は上場申請を1期遅らせるという場合もあります。
また、M&Aにおいては、未払残業の規模感と顕在化する確度の把握が重要です。違法性が極めて高く、全く対策が講じられていない場合は、発生リスクの高い簿外債務になりますので、財務DDにおいて考慮される要素になりますので、ディールへの影響を検討することになります。
また発生リスクが低い場合であっても、M&A後に、労務管理の見直し・統合を進めることになりますので、どの程度の作業になるかの見通しをもって置くことが必要です。
◆付加金
労働基準法114条
裁判所は、第二十条(解雇予告手当)、第二十六条(休業手当)若しくは第三十七条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項(有給休暇の賃金)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
未払残業問題を高額化、深刻化させる要因の一つとして、付加金制度があります。裁判実務上、付加金の支払いの命令は、原告が請求をしないと認められないものとされています。従業員個人レベルの紛争では、ほとんど問題になりませんが、従業員が代理人(弁護士)を立てて請求してくる場合は、ほぼ必ず請求に入ってくることが一般的であり、実際の未払債務以上に金額が膨らむことになります。
ただし、付加金の支払命令の前に、使用者が未払賃金を全額支払った場合は、付加金支払いを命じることはできません。(細谷服装事件・最判昭和35.3.11)
◆遅延損害金
未払賃金の遅延損害金は、商事法定利息6%が適用されます。(商法514条)ただし、退職者の場合は、賃確法6条1項により退職日の翌日から原則として14.6%となりますので、注意が必要です。
退職者との紛争において、解決までの時間がかかる場合や、過去の蒸し返しになる場合などは遅延損害金が加わることで、思わぬ金額に膨らむことになります。
IPO準備支援、M&Aのデューデリジェンス(労務監査)の
お問合せはこちらから
お問合せやご相談は、お問合せメールフォームにて受け付けております。
まだ案件化していない場合でも、まずはお気軽にご連絡ください。

新着情報
2026年01月30日
[経営全般[助成金]]
ブログ更新
2026年01月28日
2/2-6セミナー受付終了