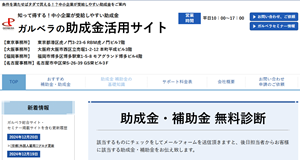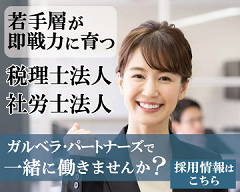IPO準備支援、M&Aの労務デューデリジェンスはお任せください

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ
労務監査.com
【東京事務所】東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
【大阪事務所】大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
【福岡事務所】福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
【名古屋事務所】名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
IPO・M&Aの労務監査
お気軽にお問合せください!
未払残業問題をいかに処理するか!?
IPOまたはM&Aを問わず、労務デューデリジェンスが実施されるほとんどのケースで、未払残業問題が発覚します。
金額の過多、違法性の強弱、社内のコンプライアンス意識など差異はありますが、DD後の対策は必須です。
M&Aでは、未払残業は偶発債務として認識され、減額交渉や表明保証が必要になる場合もあります。
IPO準備支援では、程度に関わらず、原則として未払残業問題の存在自体が許されず、場合によっては精算の対象になります。精算による経済的負担や労働基準監督署の臨検リスクを最小化するように、専門のコンサルタントがご案内いたしますのでご安心ください。
以下では、未払残業になりやすいパターンの一例をご紹介いたします。
残業代単価の計算式の誤り

労働基準法施行規則第19条
月給制の場合は、所定賃金を月平均所定労働時間で割った金額を単価として残業代を計算します。
問題は「所定賃金」と「月平均所定労働時間」です。
(1)所定賃金の注意点
一般的な給与規程では「所定内」または「基準内」というような表現が使用され、その意味合いとしては次のように定義されています。
「所定内給与」:毎月決まって支払われる賃金(固定部分)
「所定外給与」:基本給・諸手当以外の割増賃金(変動部分)
「基準内賃金」:基本給・諸手当等の固定部分(通勤手当除く)
「基準外賃金」:通勤手当および割増賃金、臨時の賃金
一般に、通勤手当を除いた基準内賃金を「(残業代計算の)所定賃金」としている賃金規程が多いのですが、まれに精勤手当や職務手当という名目で控除されている例が見られます。またそもそも曖昧になっており、基本給のみを「所定賃金」としている場合もあります。
この場合、残業代単価が不当に定額になり、恒常的に未払が発生する状況になります。社員一人、その月だけではたいした金額にはなりませんが、塵も積もればたいへんな未払債務になる場合があります。計算違いによる未払は、明白な未払債務になるので注意が必要です。
<残業代計算の「所定賃金」から除外できるのは以下の賃金のみです>
・家族手当扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当に限る
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当(実質的に住宅に要する費用に応じて支給されているものに限る)
・残業代として払われた臨時の賃金、インセンティブ、賞与など
(2)月平均所定労働時間
次の計算式で計算されます。
月平均所定労働時間 = 勤務カレンダーの所定労働日 × 所定労働時間 ÷ 12カ月
多く見られる例としては、年間休日数が不明確なもの(何となく週休2日制)や、勤務カレンダーで定めると規定しておきながら、カレンダーが存在しないケースです。
一般的には160~170時間程度になる場合が多いので、何となく給与計算ソフトに入力していると、不正確な計算となり、金額の不足が発生することがあります。
残業について法的な検討を進める前提として、これらの計算が誤っている場合は、この段階で未払が発生することになりますのでご注意ください。
労働時間の二重管理の危険性

多くの企業では、出社・退社管理にタイムカードや静脈認証を使用しておりますが、これとは別に労働時間を管理している場合は、ダブルスタンダードとみなされる危険があります。
タイムカードの時刻とは別に「スケジュール管理ソフト」「労働時間報告書」「出勤簿」を使用してい場合であってタイムカードの時間から大きく乖離している場合は、サービス残業の疑いありと指摘される危険があります。
また会社によっては「残業許可制度」「自己申告制度」「労働時間報告書」などによって別途労働時間を申告している場合があります。
会社が適正と認めない残業は、勝手な居残りであるので認めないとして、タイムカードや出退勤記録を修正しているような場合は、厳密な運用が必要です。
残業代について紛争になった場合は、本来は未払残業を主張する労働者に立証責任があるのですが、会社には労働時間の管理義務があります。(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」平成13年4月6日基発339号)
労働者が主張した労働時間を会社が否認する場合には、その内容を主張・立証する必要があり、勝手な居残りである等の理由で漠然とした反証は認められないのが実情です。
また残業許可制を理由に、労働者の主張を否認しようとする場合であっても、無断残業を黙認し、その労働の成果を受領しながら、後から無許可残業を主張するのは、社会通念からしても苦しい主張となります。
このように、「会社の主張=会社が認めた労働時間」「労働者の主張=在社時間」となった場合には、労働者の主張する時間が認められやすく、タイムカードが存在しない場合は以下のような方法で、合理的と判断される時間が計算されてしまう場合があります。
① 入退館セキュリティ記録
② パソコンのログイン・ログアウト記録
③ 電子メールの送信記録
④ タコグラフ
⑤ 開店・閉店時間
⑥ 労働者のメモ、配偶者の証言
残業の管理は、会社にとっては頭の痛い問題ですが、だからといって見て見ぬふりをして曖昧にしていると、曖昧であることが会社にとっては基本的に不利に働くことになります。
管理監督者を主張するリスク

労働基準法第41条第2号にいう「監督若しくは管理の地位にある」(いわゆる管理監督者)には、残業代に関する規定が適用除外になることは一般に知られています。
残業管理に悩む中小企業においては、役職がついている者を全て管理監督者として残業代が未払になっている事例もあり、社員数によっては大規模な簿外債務になるケースもあります。
日本マクドナルド事件に代表される、「名ばかり管理職」が問題になり、多くの企業ではコンプライアンス上、管理監督者の濫用は少なくなっていますが、未だに対策ができていない企業も多く見られます。
しかしながら、残業代についてのトラブルが発生した場合に、管理監督者が認められるのは、下記の基準を満たした、ごく例外的な従業員に限られます。
<管理監督者として認められる基準の例>
①労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。
②労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。
③管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。
④管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。
こうした基準を理解せず、管理監督者を主張するケースが多いのですが、判例上認められた例も少なく、またあまりに安易に管理監督者を主張する会社が多いためか、裁判実務上は裁判官や相手側弁護士にはほとんど相手にされないというのが実態のようです。
また労働基準監督署の臨検事例も同様で、管理監督者の主張をしても、労働基準監督官から相手にされず、お構いなしに是正勧告書が交付されたという話も聞かれます。
近年のこうした傾向を踏まえ、残業マネジメントにおいては、管理監督者とすべき者については相応の処遇と権限を付与していただき、それ以外の社員は定額残業代など、別のロジックで対応するといった、きめ細かな対応が求められていますし、就業規則・給与規程と人事運用を合わせていくことも必要になります。とりわけ上場申請では、こうした対策が重要です。
なお蛇足ですが、管理監督者であっても、深夜割増は必要ですし、健康管理の観点から出勤時刻や退勤時刻の管理は必要と解されています。管理監督者ということで、タイムカードも押さず放任するということはとうてい許されるものではなく、そのような場合は、会社がたいへん不利になることでしょう。
その他 残業に関する論点

◆ 変形労働時間制の誤った運用による未払
(1か月単位、1年単位、フレックスタイム)
◆ 振替休日と代休を混同した取扱いやそもそも法定休日の定めが曖昧で休日出勤が正しく把握されていないケース
◆「準備時間」「待機時間」「仮眠時間」「移動時間」の不適切な運用による未払
◆ 月間60時間超の残業
中小企業は平成31年3月まで猶予される予定ですが、大企業については、月間60時間超の残業は150%割増となります。また、月間60時間という残業水準は、特別条項付き三六協定を締結しない限りはそもそも違法ですので、ご注意ください。
◆みなし労働時間について
労働基準法第38条の2において「労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と定められています。これを外勤の営業職等に適用して、どんなに働いても8時間の所定労働時間で計算するという運用をしている会社がまれにあります。
しかし、スマートフォン・携帯電話が一般化した近年において「労働時間を算定し難い」といわれる状況はほとんどないといえるでしょう。(海外出張など一部の例外を除き)
専門家の間では、この規程は歴史的役割を終えたと評価する意見が多くなっています。みなし労働時間を一律適用しているような会社があれば、早急に見直しが必要です。
IPO準備支援、M&Aのデューデリジェンス(労務監査)の
お問合せはこちらから
お問合せやご相談は、お問合せメールフォームにて受け付けております。
まだ案件化していない場合でも、まずはお気軽にご連絡ください。

新着情報
2026年01月30日
[経営全般[助成金]]
ブログ更新
2026年01月28日
2/2-6セミナー受付終了